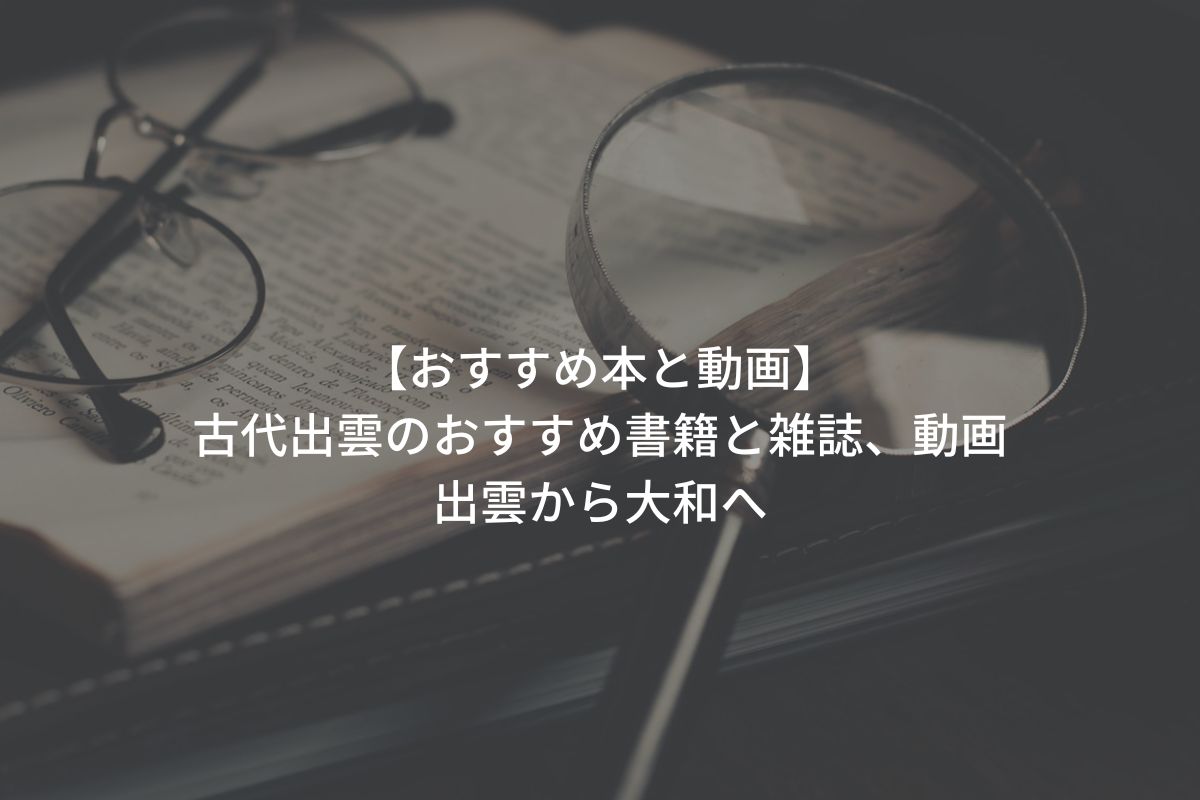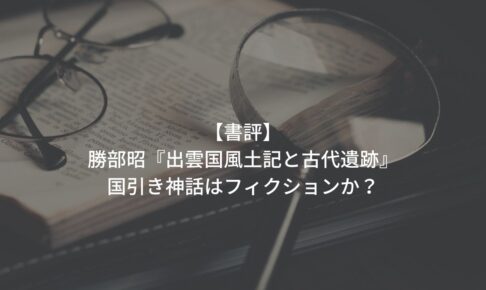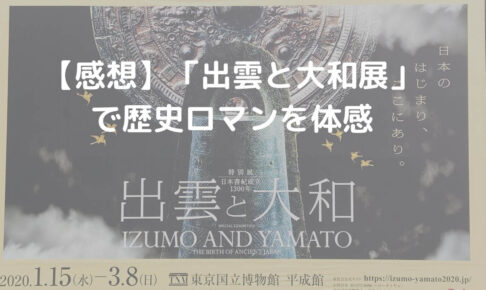この記事では、古代出雲に関心のある方などにオススメしたい図書と雑誌、動画をご紹介していきます。
今回は、古代日本を治める主役が出雲から大和へ移動していく様子を知る助けとなるコンテンツを中心に選んでおります。
これらのコンテンツは、邪馬台国の所在地から神武東征の真偽、ヤマト王権の成立などをさらに知るきっかけとなっていきます。
【図書】村井康彦『出雲と大和─古代国家の原像をたずねて』岩波新書 2013年
本書の魅力的なところは、村井氏は文献史学から考古学、民俗学に至るまでの広範囲に渡る知見やフィールドワークを通じて、次のような大胆な説を提示していることです。
【村井説その1】出雲勢力はヤマト王権成立以前に大和の地を支配
村井氏は、出雲勢力がヤマト王権成立以前から大和を支配していたとして、次の事例をあげて自説を展開しております。
1つめは、大和の三輪山に祀られている神が、出雲の大国主神と同じ神であること。
2つめは、8世紀に出雲国造が朝廷で奏上した「神賀詞」(かむよごと)で、出雲系の4神(三輪山の大神神社、葛城の高鴨神社、伽夜奈流美の神、宇奈手の神)を「皇孫の命の近き守り神」として、皇室の守り神としていること。
【村井説その2】卑弥呼はヤマト王権と無関係
村井氏は、卑弥呼および邪馬台国がヤマト王権やのちの天皇家とはつながらない勢力である理由として『古事記』や『日本書紀』に卑弥呼の記述がないことをあげております。
【村井説その3】「神武東征」は歴史的事実
村井氏は、自身による調査分析によって下記の結論を導き出し、「神武東征」は歴史的事実であるという自説を展開しております。
- 邪馬台国の所在地は大和で、主力は出雲系だった。
- 出雲系の人々は、ヤマト王権成立以前から大和の地を支配していた
- 出雲系の人々は、日向系の人々の「神武東征」による攻撃を受けた。
- 大和盆地での戦いが膠着状態になったため、和議により「国譲り」が行われた。
【雑誌】『時空旅人 2020年 1月号 Vol.53』三栄書房 2019年
こちらは雑誌で、『日本書紀』成立1300年 出雲と大和というテーマで特集を組んでおります。オールカラーでわかりやすい説明が特徴です。
本書の構成は、特別展「出雲と大和」の展示構成を意識した、
- 「古代祭祀の世界」出雲
- 「王権誕生の地」大和
などの章立てになっており、来館時のイメージと重ね合わせやすくなっております。
また巻頭ページでは、東京国立博物館考古室長の品川欣也氏(2020年1月現在)が「古代史への誘い」というテーマで寄稿されております。「出雲と大和」展の展示構成に沿って、作品(史資料)の見どころについてコンパクトにわかりやすく解説しております。
Kindle Unlimited会員の方は無料で読めます。
【動画】『NHKスペシャル』「巨大神殿は実在したのか〜古代・出雲大社のナゾ」
こちらは2001年に『NHKスペシャル』で放映されたドキュメンタリー番組の動画です。
この動画では、2000年に出雲大社の境内から発掘された巨大柱をきっかけに、当時は伝承に過ぎないと考えられていた巨大神殿が実在する可能性を裏付けていくプロセスを見ることができます。
発掘調査では、柱を直接地下に埋めた掘立柱(ほったてばしら)とよばれる工法が使われていることがわかりました。しかしその穴の深さはわずか2m。
このような工法で本当に高さ48mと推定された巨大神殿を支える強度が得られたのか?
専門家の謎は深まります。
その疑問を大林組を中心に解き明かしていく様子が見どころです。
NHKスペシャル 巨大神殿は実在したのか ~古代・出雲大社のナゾ~出雲の考古資料は「国譲り」と「神武東征」神話を再考する機会に
東京国立博物館の特別展「出雲と大和」では、出雲が独自の祭祀文化を持っていたことを示す数多くの考古資料を見ることができます。下記はその主な考古資料です。
- 出雲大社境内から出土した巨大な柱(宇豆柱、心御柱)
- 荒神谷遺跡から出土した銅剣358本のうち168本、銅鐸6個のちの5本、銅鉾16本
- 加茂岩倉遺跡から出土した銅鐸39個のうちの30個
『古事記』や『日本書紀』に記述されている出雲の「国譲り」や「神武東征」などの神話をフィクションとして切り捨てて良いのか違和感をお持ちの方もいると思います。
このような疑問について、「出雲と大和」展やこれらの書籍を通じて新たな気づきをもたらすきっかけになるはずです。
これらの書籍と雑誌、動画をおすすめする方
ご紹介したこれらの書籍と雑誌、動画は、このような方にお役に立つと信じております。
- 出雲の「国譲り」を含む『日本書紀』の神話に関心のある方。
- 『日本書紀』の神話はすべてフィクションなのか?という疑問を持っている方。
- 古代出雲に関心のある方
おすすめの図書と雑誌、動画リスト3選
以上、おすすめの図書と雑誌、動画のご紹介でした。ご参考になれば幸いです。